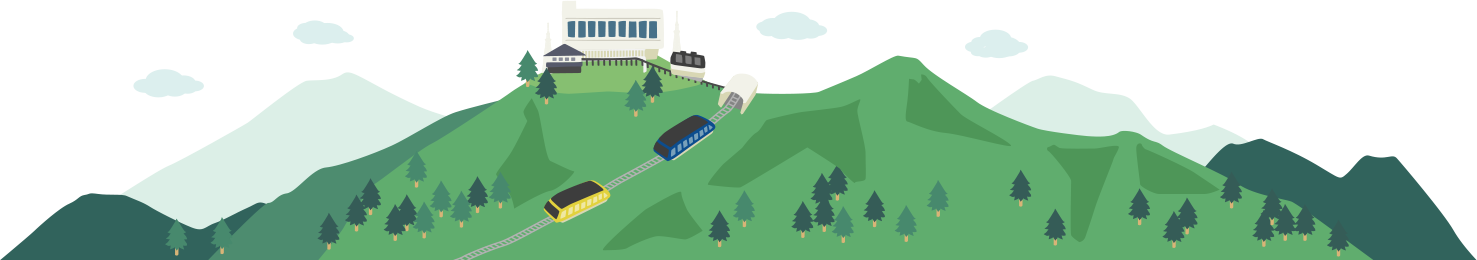身体拘束ゼロをめざして
身体拘束最小化の取り組み
身体拘束の対象となる具体的な行為は下記のような例示があります。
- 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように指の機能を制限するミトン型の手袋をつける。
- 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
- 脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
- 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
- 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
当院では身体拘束を行わないために、テレビ・音楽鑑賞、塗り絵や読書など個人に合った時間の過ごし方を考え、車椅子に乗れる方は、車椅子で過ごせる環境を整えるようにしています。また、オムツを外す方はオムツ内の皮膚保清、トイレ誘導の時間やオムツ交換時間の検討を行い、オムツを外す要因の除去に努めています。
チューブ類の自己抜去予防には、チューブの固定方法や位置(視界に入らない、触れない)の工夫、皮膚の清潔保持に努めています。しかし、患者さんの生命維持のため、緊急やむを得ない場合においてのみ身体拘束を行っており、殆どはチューブ類の自己抜去予防です。
経鼻経管栄養剤注入中の自己抜去は栄養剤が気道に流入し窒息や肺炎を起こす危険があります。また、気管カニューレの自己抜去は、出血や気管切開孔の閉塞による呼吸困難を起こす危険があります。このような場合にのみ身体拘束を行っていますが、行う際には、家族へ説明し、同意を得た上で、緊急やむを得ない3要件(切迫性・非代替性・一時性)に該当しているか、人権委員会で身体拘束の妥当性を審議しています。
身体拘束実施中は毎日、身体拘束による心身状態の観察と解除に向けた検討を行い、週1回以上は多職種でのカンファレンスを実施しています。また、3ヶ月以上身体拘束を継続した場合は、3ヶ月ごとに報告書を提出して承認を得るなど、身体拘束が漫然と行われないようにしています。
身体拘束を考えるうえで大切なことは、「身体拘束は本人の行動の自由を制限し、尊厳を損なう行為」ということを認識することです。身体拘束は多くの弊害をもたらし、身体拘束による悪循環を生じてしまいます。このことに意識を向け、可能な限り身体拘束をしないケアの実現に向けて、院内研修や委員会活動を行い、院内全体で身体拘束最小化に取り組んでいます。
チューブ類の自己抜去予防には、チューブの固定方法や位置(視界に入らない、触れない)の工夫、皮膚の清潔保持に努めています。しかし、患者さんの生命維持のため、緊急やむを得ない場合においてのみ身体拘束を行っており、殆どはチューブ類の自己抜去予防です。
経鼻経管栄養剤注入中の自己抜去は栄養剤が気道に流入し窒息や肺炎を起こす危険があります。また、気管カニューレの自己抜去は、出血や気管切開孔の閉塞による呼吸困難を起こす危険があります。このような場合にのみ身体拘束を行っていますが、行う際には、家族へ説明し、同意を得た上で、緊急やむを得ない3要件(切迫性・非代替性・一時性)に該当しているか、人権委員会で身体拘束の妥当性を審議しています。
身体拘束実施中は毎日、身体拘束による心身状態の観察と解除に向けた検討を行い、週1回以上は多職種でのカンファレンスを実施しています。また、3ヶ月以上身体拘束を継続した場合は、3ヶ月ごとに報告書を提出して承認を得るなど、身体拘束が漫然と行われないようにしています。
身体拘束を考えるうえで大切なことは、「身体拘束は本人の行動の自由を制限し、尊厳を損なう行為」ということを認識することです。身体拘束は多くの弊害をもたらし、身体拘束による悪循環を生じてしまいます。このことに意識を向け、可能な限り身体拘束をしないケアの実現に向けて、院内研修や委員会活動を行い、院内全体で身体拘束最小化に取り組んでいます。