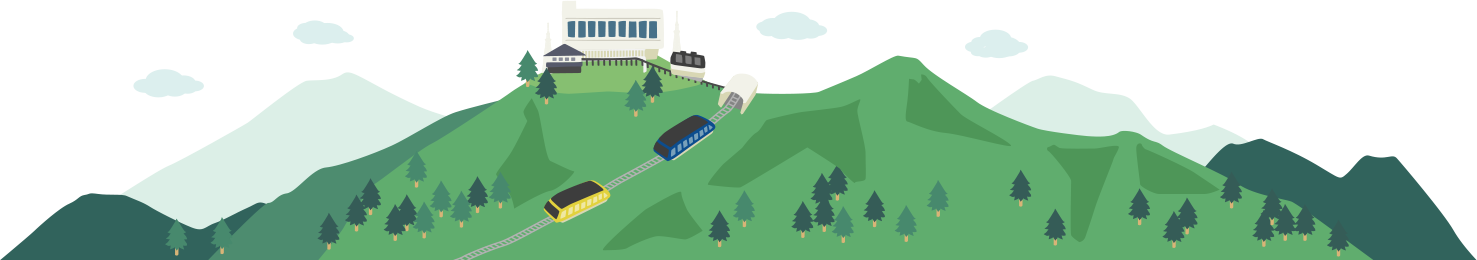リハビリテーション科

患者さん本位の「自立支援」を目指し、身体機能や日常生活活動の向上とともに、患者さんやご家族の"希望"をできるだけ叶えられるような環境を整えていきたいと考えています。
スタッフ構成は理学療法士53名、作業療法士37名、言語聴覚士9名、リハ助手4名です。(2025年4月1日現在)
スタッフ構成は理学療法士53名、作業療法士37名、言語聴覚士9名、リハ助手4名です。(2025年4月1日現在)
各部門の役割
理学療法部門の役割
身体機能や心理面などの評価を行い、全体像を十分把握した上で、運動療法(筋カや関節可動域、パランス能カなどの向上)や物理療法(温熱・電気療法など)を用いて、目常生活活動や歩行などの能カ向上を援助します。
作業療法部門の役割
今後生活していくために問題となることを的確に評価し、いろいろな作業活動(陶芸・木工・手芸・革細工など)を用いて機能の回復や維持を促し、治療・援助を行います。また障害があっても、残された機能を最大限活用し、身辺動作や家事動作の能カ向上、職場への復帰などを目指した練習を行います。
言語聴覚療法部門の役割
"コミュニケーション"に於いては、「聴いて理解する」「話す」「文字を読む」「文字を書く」ことが困難になる失語症、発生発語器官の運動障害により、話言葉の発音が不明瞭になる運動障害性(麻痺性)構音障害などがあります。"食べること"に於いては、嚥下に関係する筋肉や神経の障害により、食物が食べられない、誤嚥してしまう摂食・嚥下障害があります。これら"コミュニケーション"や、"食べること"に障害を負った方々に対して、機能の獲得・回復・維持を促し、治療・援助を行います。
スタッフ教育とプロジェクトチームの活動
新しく入職したスタッフの教育にはプリセプター制度を導入しています。研修は、本部主催の研修と院内の研修を行っております。また症例検討会や勉強会を毎月開催し、文献抄読会、学会出張の報告会も随時開催しております。
将来のリハビリテーション科の方向性を考えるプロジェクトチームを立ち上げ、療法や経験年数の枠にとらわれない自由な発想を出し合う場を定期的に設け、活動を行っています。
将来のリハビリテーション科の方向性を考えるプロジェクトチームを立ち上げ、療法や経験年数の枠にとらわれない自由な発想を出し合う場を定期的に設け、活動を行っています。
チーム医療への参画
医療安全対策チーム
医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、放射線技師、臨床検査技師、事務職とともに院内ラウンドを行い、医療安全に関する問題点を指摘し、院内の安全で質の高い医療提供体制の確立を目的に活動しています。リハスタッフは主に車椅子に関する点検、整備に関わっています。
院内感染対策チーム
医師、看護師、薬剤師、管理栄養士とともに院内ラウンドを行い、院内感染の発生と拡大を未然に防ぐことを目的に活動しています。
リハスタッフは主に院内の消毒液や院内感染物の管理について確認を行っています。
リハスタッフは主に院内の消毒液や院内感染物の管理について確認を行っています。
栄養サポートチーム
医師、看護師、管理栄養士、薬剤師、歯科衛生士、臨床検査技師、言語聴覚士にて、患者さんの栄養管理を包括的に支援することを目的に活動しています。リハスタッフでは言語聴覚士が嚥下機能の評価や食事形態の決定などに関わっています。
褥瘡対策チーム
医師、看護師、リハスタッフ、薬剤師、管理栄養士にて褥瘡回診を行い、褥瘡のある患者さんや褥瘡予防が必要な患者さんに対してのケアや処置に対しての指導を行います。リハスタッフは主にポジショニングの評価、検討に関わっています。
各病棟での役割
在宅支援での役割
訪問リハビリテーション

当院から退院された方、神経難病で外来受診されている方を対象に理学療法士、作業療法士がご自宅を訪問してリハビリテーションを実施します。
身体機能面だけではなく排泄動作、入浴動作、家事動作、外出練習など、実際の日常生活に向けて支援を行っています。また、必要な福祉用具の選定や環境設定などのアドバイスも行っています。ご利用者さんに合わせてリハビリテーションを行いご自宅で過ごせるように支援させて頂きます。
身体機能面だけではなく排泄動作、入浴動作、家事動作、外出練習など、実際の日常生活に向けて支援を行っています。また、必要な福祉用具の選定や環境設定などのアドバイスも行っています。ご利用者さんに合わせてリハビリテーションを行いご自宅で過ごせるように支援させて頂きます。
地域支援事業
当院は北九州市の地域リハビリテーション協力機関となっており、以下の活動に参加しております。

具体的な活動内容
- 地域包括支援センターが主催する地域ケア個別会議へのアドバイザー参加
- 高齢者サロンやクラブ活動等、地域活動の場での介護予防の啓発
- 地域リハビリテーション支援センターが主催する連携会議への参加